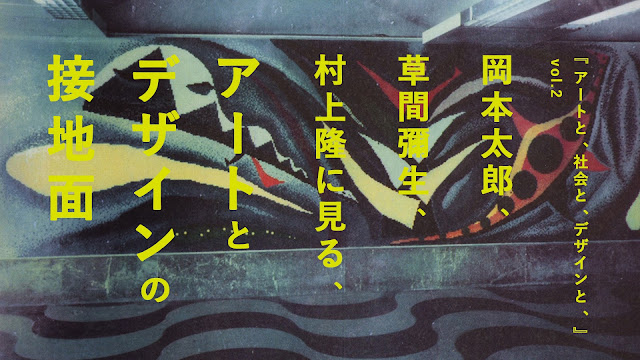岡本太郎、草間彌生、村上隆に見る、アートとデザインの接地面
「アートと、社会と、デザインと」
vol.2 岡本太郎、草間彌生、村上隆に見る、アートとデザインの接地面
日時:2020年1月25日(土) 17:00-19:00
定員:20名
参加費:1,000円
講師:伊村靖子 〈情報科学芸術大学院大学(IAMAS)講師〉
「生活の芸術化」を掲げたのは、ウィリアム・モリスをはじめとする先人たちです。技術と社会の関係が変わろうとする時、総合芸術やトータル・デザインについての議論がさかんになります。誰のための芸術か、日常の中の芸術とは何かという鋭い問いが、時代の切断面として立ち現れるのです。絵画や彫刻にとどまらず、日用品や家具、建築を通して都市の中に芸術が流通していったのも決して偶然ではないでしょう。
このような作家の例として、岡本太郎(1911-1996)、草間彌生(1929-)、村上隆(1962-)が挙げられるのではないでしょうか。岡本太郎は、マスメディアの中の芸術家像を生み出し、草間彌生は、絵画を超えてマグカップや家具などに水玉を展開させ、世界を覆い尽くす方法を見出しました。村上隆は、「スーパーフラット」を提唱し、芸術の制度を脱構築した新たな美学を打ち立てています。彼らの活動を切り口として、アートとデザインの接地面にある批評精神を探ります。
伊村靖子
伊村靖子(いむらやすこ/ 情報科学芸術大学院大学(IAMAS)講師)
国立新美術館アソシエイトフェローを経て、2016年より現職。近年は、美術とデザインの関係史に関心を持つ。共編に『虚像の時代 東野芳明美術批評選』(河出書房新社、2013年)。論文に「「色彩と空間」展から大阪万博まで──六〇年代美術とデザインの接地面」(『美術フォーラム21』第30号、2014年)など。関わった展覧会に「美術と印刷物──1960-70年代を中心に」展(東京国立近代美術館、2014年)、岐阜おおがきビエンナーレ2017「新しい時代 メディア・アート研究事始め」(IAMAS、2017年)など。
1月25日開催の、IAMAS
伊村靖子さんによるレクチャーシリーズ『アートと、社会と、デザインと、』の第2回目『岡本太郎、草間彌生、村上隆に見る、アートとデザインの接地面』にご参加くださった皆様、ありがとうございました。
さて、“アートとデザインの接地面”と題しましたが、そもそもアートとデザインの違いとは何なのでしょう? 様々な分野を横断的に見据え、テクノロジーとアートの融合を目指すIAMAS (情報科学芸術大学院大学/岐阜県大垣市) で教鞭を執る伊村さんは「日ごろ学生と会話をするなかで、その実、そこに違いは無いのではないか、とも思える」と前置きされた上で、今回も、伊村さんが研究をされている批評家
東野芳明(1930年-2005年)からお話がはじまりました。
東野芳明が1966年に南画廊で企画した『色彩と空間』展のカタログに寄せたテキスト『美術とデザインの間』には、こんなことが書かれています。(*1)
・・・
『それにしても、最近では、デザインとも美術とも名付けようのない作品が美術界にもぼつぼつとあらわれて、われわれをマゴツカセはじめている。(中略)美術がひとりの個⼈の何らかの⾃⼰表現であることは当然にしても、その作者の⾃我の表現が、いつも表現主義的な押しつけがましいドロドロした表情をもっていないと、これをデザイン的だときめつける考え⽅こそ、低次の表現主義に災いされた狭くるしい⾒⽅であろう。』
『デザインは匿名的で量産可能であり、美術は個⼈の表現で原作⼀点主義である、という区別も横尾忠則のような⼤へん個性的なデザイナーがあらわれる⼀⽅、⾮個性的な美術が⽣れ、また、シルクスクリーンなどの⼿法がとり⼊れられたポップ・アートの量産可能な作品を考えると、この区別はますますつけにくくなってきている。むしろ、われわれは、デザインと美術という固くるしい差別を⼀度御破算にして、どちらも芸術として眺めなおして⾒る⽅が必要なのではあるまいか。』
(*展覧会カタログより抜粋)
・・・
 |
| 「⾊彩と空間」展 ポスター (1966年9⽉26⽇―10⽉13⽇、南画廊) |
『デザインと美術という固くるしい差別を一度御破算にする』(*1)。この東野の言葉は、南画廊の平面図に、サム・フランシス、アン・トゥルーイット、磯崎新、五東衛、⽥中信太郎、三⽊富雄、⼭⼝勝弘、湯原和夫の8作家それぞれの作品の“設計図”をトレースした、展覧会ポスターの斬新なデザインにも見てとれるように、“作品を発注制作する”というコンセプトに沿って行われました。(ちなみに五東衛は、後の清水九兵衛。)いまでこそ発注制作もひとつの手法となりましたが、『美術は個人の表現で一点主義である、という区別』(*1)がなされていた当時、作家が他者に制作を委ねることは珍しいことでした。伊村さんは「個人での加工が難しいプラスチックのような新素材の登場も、作家の制作意識に影響を与えたのではないか」としながら、「アーティストとデザイナーが同じ制作姿勢に立つ」、つまり「アーティストが設計(デザイン)すること」を試みた実験的な展覧会であったことが紹介されました。参加作家のひとり、耳の彫刻で知られる三木富雄が、耳を抽象化したメタリックブルー(!)の作品を出品するなど、作家にとってもチャレンジングな機会だったことが伺われます。
“デザイン”というと、グラフィック・デザイン、インダストリアル・デザイン、ファッションデザイン、など、それぞれの分野と専門性があり、“美術”と分けて捉えがちですが、デザインとは本来“design=設計”することです。
・・・
『デザイン』という言葉を、現在混乱した使われ方から語源にまで還元するならば、それは「あるものを作る場合に心のなかに描かれた計画あるいは図式。行為によって実現されるべき観念(アイデア)の予備的な概念」ということである(オックスフォード辞典による)。』(*1)
『(中略)作者の制作は設計図を厳密に描く段階で完了している。そこには、恣意や偶然や自発性の自由は禁じられている。物体や行為によって具現化される以前の、観念の状態の図式だけに厳しく立ちはだかること−−−これが作家たちの自らの「自由」に課した条件であった。そこには、物体や行為との衝突から生れる恣意や偶然や自発性をこそ、自我表現の不可欠な要素と見做す抽象表現主義への、ひとつの反省がみられると言ってよいかもしれない。』(*1)
・・・
 |
| 岡本太郎『日の壁』(1957年) 旧東京都庁舎 設計:丹下健三 |
ここで伊村さんから「芸術における設計とは?」、「複製時代の芸術とは?」というキーワード挙げられ、“アートとデザインの接地面”について、アーティストの活動を通じて更に考えるべく、まずは岡本太郎(1911年-1996年)から取り上げられました。
19才でパリに移り住み、制作のかたわら哲学や民俗学を学ぶなどして視野を広げていた岡本太郎は、帰国後、同時代の建築家と多くの交流を持ちます。また建築家の間でも『生活の芸術化』を提案しようという動きが見られ、1955年に日本橋高島屋で『ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン3⼈展』として、坂倉準三が展示設計を手がけた展覧会が開かれます。その後、岡本は坂倉からの依頼で日本橋高島屋地下通路に陶壁画を設置(1952年)。これが岡本にとって、公共空間に制作を行う初の試みとなりました。1953年には、日本のグッドデザイン運動の先駆けとなる『国際デザインコミッティー(現・⽇本デザインコミッティー)』を発足し、顧問に坂倉準三、前川国男、シャルロット・ペリアン、建築からは丹下健三、清家清、吉坂隆正、デザインは柳宗理、剣持勇、渡辺⼒、⻲倉雄策、写真は⽯元泰博、絵画は岡本太郎、評論からは瀧⼝修造、浜⼝隆⼀、勝⾒勝ら、各分野の錚々たるメンバーが集まり、定期的に接点が持たれました。
そして岡本は1957年、丹下健三設計の旧東京都庁舎において『日の壁』を手がけることになります。丹下の設計断面図には、岡本の作品設置プランが最初から組み込まれており、設計の段階からアーティストが関わる協働によって実現していく様子が伺えます。ほかにも、雑誌『総合』(1957年6月号)に丹下健三、磯崎新とともに『ぼくらの都市計画』を発表、またアントニン・レーモンドとの『デッブス邸茶室』(1962年)、磯崎新が会場構成を担当した『岡本太郎展』(西武百貨店、1964年)なども見られます。岡本太郎は、建築家やデザイナーとの仕事を通じて建築にアートを付随させることで、生活空間でのアートの在り方を提示する「コミッションワーク」の礎を築いた作家のひとりと言えます。また『グラスの底に顔があっても良いじゃないか』の岡本の言葉が示すように、椅子やグラスなど日用品のデザインも多く手がけ、自身の作品を日常生活に直接持ち込むことを試みたのも、岡本太郎が最初だったのではないでしょうか。
次に草間彌生(1929年−)です。
1957年、28歳で渡米し、活動の幅を世界に広げた草間彌生は「都市空間へ進出した作家」と言えるのではないかと、伊村さんは指摘します。街中で行われた、性をモチーフとした過激なゲリラ的パフォーマンス『クサマ・ハプニング』は、タブーを都市に持ち込むことで「アートと日常との境界を消滅」させる行為として、衝撃的に受けとめられたことで知られています。そのなかで伊村さんは、都市空間をパフォーマンスの舞台とすることで、アートと日常をつないでみせた草間彌生の活動のなかでも、特に写真の重要性について指摘されました。作品の前でのセルフポートレートや、先の『クサマ・ハプニング』の様子など、写真に残されているものが多い作家ですが「そこには単なる記録写真以上の作家の意図が見てとれる」と伊村さんは言います。例えば、『《集合̶千のボート・ショー》のインスタレーションの中に⽴つ草間』(1963年、ニューヨーク、ガートルード・スタイン画廊、撮影:Rudolph Burckhardt)では、立体と、壁面のシルク作品(版画)の前にヌードで立つ草間が写っています。これについて「作品と自分自身を配置、デザインして空間として見せる、ということを、写真という1点で成立してみせている」、「写真にすることで、イメージとしてあらゆる媒体を通じて流通させることができる」、つまり「ものを作るだけでなくイメージを拡散させることができるのだ」と。草間が戦略的に「写真を設計、デザインしていた」という鋭い見解は、写真のなかの草間彌生の独特な佇まいにのみ目が向いていた筆者には無かった視点で、作品を読み解くとはまさにこうであるというような、批評家の目の鮮やかさを思い知るところとなりました。また「写真を介して自身の世界観が拡張し増殖していく」様子は、草間彌生の代名詞とも言える水玉やネットや、ソフトスカルプチャーが増殖していく様をも彷彿させます。
そしてまた草間の「設計」は、写真表現だけにとどまらないと、更にお話がつづきます。それは彫刻単体ではなく、観客にどう働きかけるのか、という、パフォーマンスとしての優れた“空間設計”にあると言います。1975年にアメリカから帰国し、しばらく表舞台から遠ざかっていた時期を経て、再評価のきっかけとなった代表作とも言える『インフィニティ・ミラーズ』(1965年)。その1989年の再制作で“インスタレーション”作品として「観客との関係を上手く設計してみせたことで、作品にある種のエンターテイメント性が生まれ、多くの支持を得たことが、その後の展開につながっているのではないか」と話されました。
また草間彌生と同時代のアメリカで主流だった、ポップ・アート、ミニマル・アートにおいて、アンディー・ウォーホルが『Factory』と呼んだ工場で作品を量産したり、マスメディアの環境を意識した作品の提供を行い、ドナルド・ジャッドは絵画、彫刻、シルクスクリーン、家具など両義性をはらんだ制作を通じて、大量生産品のデザインに対する提案、美意識が提示されたことにも、言及されました。
 |
| 村上隆「スーパーフラット宣言」(2000年) |
そして3人目は村上隆(1962年−)です。
村上隆は、2000年の『スーパーフラット宣言』を起点として「成熟しきった消費社会で、どう活動、表現するか」を、次々に計画、設計、実行してみせている、と言えるのかもしれません。『ヒロポンファクトリー』を前身に、2001年に立ち上げられた『有限会社カイカイキキ』は、かつての日本画の工房や、同時代のアニメーション・スタジオを思わせる仕組みをとりながら、芸術に関する事業の総合商社として、様々に展開しています。その一つ『GEISAI』もまた「美術市場の発展を目指し、発表、流通、評価の場が、村上隆によってデザインされた」と考えられます。
そして「冒頭の『色彩と空間』展が行われた60年代に、新素材として登場したプラスチックが、それまでの制作手法を変化させたように、村上隆がサンプリング、リミックスの手法で、日本美術を取り入れてみせたり、作品そのものを自立させるのではなく、コンテンツとしてどのように流通させるかを示してみせたグルービジョンズなど、Windows95の発売によって、パソコン環境が一般的に普及した90年代を境に、作品の在り様が変化した」としながら、「それを使用して制作すること以上に、パソコンやインターネットという新しいメディアの在り方そのものの影響が見られるようになったのでは」と示されました。
また、その影響はアーティストだけでなく、伊村さんが『美術手帖』へ寄稿したテキストでは「1990年代以降、もっとも変化したのは、作品と鑑賞者の関係である。」と指摘(*2)。つづいて「ロラン・バルトは『作者の死』(1967)において、『作者の死』に代わる『読者の誕生』を提起したが、鑑賞者の能動的な関わりが技術によって促され、試されたのが、2007年以降のメディア環境の変化だろう。」(*2)と、作品は作者に支配されるものではなく「鑑賞者がどのように解釈するか」への移行によって『読者の誕生』がうながされる、というロラン・バルトの言葉を引きながら、その契機となった例として「pixivは、イラストに特化したSNSとして2007年に始まったオンライン・コミュニティである。二次創作を含め作品を投稿し、制作者に限らずほかの利用者がリアクションすることで、ネットワークが形成されていく。」と記しています。(*2)アニメ『エヴァンゲリオン』のキャラクター綾波レイの“ガレージキット”のように、2次元上の存在を3次元に置き換えデフォルメを加えながら、ファンがイメージを育てていく“二次創作”もまた、その特徴的な事例と言えます。
その上で、哲学者 ヴィレム・フルッサー(1920年−1991年)の『デザインはartとtechnologyが⽂化の新しい形式を作るために出会う場を指し⽰し、同様にデザインが演じる役割は美術の⽣命⼒にとっても重要である。』との言葉が紹介されました。
・・・
『「ホモ・サピエンス(知恵⼈)」よりも「ホモ・ファベル(⼯作⼈)」という呼び名に注⽬し、『製作』という⾏為を⼈間のアイデンティティとみなす。』(*3)
『⼈類の歴史を「⼿の時代」「道具の時代」「機械の時代」「装置の時代」に分類。ここで⾔う「製作」とは、「所与のものから横領して、それを作り物に転換し、実⽤向きにして、役⽴てること」と定義されており、その⼿段が、⼿→道具→機械→装置へと推移していくことを指摘。道具は経験的な、機械は⼒学的な、装置は神経⽣理学的な、⼿および体のシミュレーションを指す。』(*3)
『現代は「装置の時代」であり、「機能すること」が新たな製作⽅法となった。現代の⼈間はすでに「ホモ・ファベル(⼯作⼈)」ではなく、「ホモ・ルーデンス(遊戯⼈)」であり、われわれは物を所有することにますます関⼼を失い、情報を消費することに関⼼を抱いている。』(*3)
・・・
『装置の時代』では、その『装置』に対して、われわれが何をするのかが重要であるというフルッサーの示唆は、先のロラン・バルトの『読者の誕生』にもつながります。
そして「その『装置』とは、草間彌生のインスタレーション、そしていま各所で話題になっているチームラボの試みとなって、美術にも表れている」と伊村さんは言います。そのインスタレーションのなかで、観客がどう振る舞うのかによって、作品の在り方が変わっていく、そんなひと昔前には見られなかった現象が、SNSによって引き起こされ、実際に展覧会会場に足を運ぶことなくとも、SNS上でイメージが共有され、消費されています。そして「映像作品が Youtube 上で公開されることも珍しいことではなくなった今日、本物を見るということの意味が変わってきているのではないか」、「この世にひとつしかない、1点ものの作品と対峙するより、『装置』を通じた体験の共有の意味を考えることが求められるようになっているのではないか」と、作品体験の在り方がすでに変化しつつあることを指摘しながら、従来の絵画や彫刻作品が無くなってしまう、ということは(おそらく)無いにしても「人によって求めるものや、楽しみ方、関わり方が多様化した昨今、それぞれの価値の分断、棲み分けが進むことは避けられないだろう」と話されました。
建築家やデザイナーとのジャンルを超えた協働、アーティスト・グッズの制作により生活にアートを持ち込んだ岡本太郎。街頭でのパフォーマンスや写真によるイメージ戦略による都市空間への進出、またインスタレーションにより作品と観客の関係性を変えるきっかけを示した草間彌生。サンプリング、リミックスの手法で、美術史を含めた歴史観、そして社会やメディアの動向など、あらゆる要素を取り入れ分析し、アートの土壌に設計して見せる村上隆。今回これらの作家を通じて“デザインする”ことは、私たちがイメージするところ以上の幅を持った行為であるということを、新たに確認することができたのではないでしょうか。
会場からは、挙げられた岡本太郎、草間彌生、村上隆の3作家について「最初どうしてこの3人なのか不思議だった」というお声が、ちらほら聞かれました。それに対して伊村さんは「読み手の工夫次第で、ばらばらに思えるものでも並べてみたときに、何か関係を結ぶことが出来るのではないか」と答えられました。それぞれをつなげて読み解くこと、これも‘デザイン’と呼べるのかもしれません。
また、そんな伊村さんの姿勢は『読者の誕生』そのものであり、昨年末の藤本由紀夫さんのアーティスト・トークにもつながるものでした。
「藤本由紀夫アーティスト・トーク2019」
美術も本も、ひとつの装置でしかなく、肝心なのは、それをどう読み解くのかにある。そして、わたしはこう読んだ、という実感の上に、新しい表現、新しい思考の道筋が生まれるのではないでしょうか。
今回は少し難しかったです、というご感想もあり、この報告も拙さのあまり引用が多く、何やら長くなってしまいましたが、素晴らしいお話とともに、デザイン、美術に携わる人たちに大切なメッセージを届けてくださった伊村靖子さんに、あらためてお礼申し上げます。
次回は『文化戦略としてのヴェネチア・ビエンナーレ:芸術の価値はどのように作られるのか』(仮)を予定しております。
・・・
(*1)「⾊彩と空間」展(1966年9⽉26⽇―10⽉13⽇、南画廊)
展覧会カタログテキスト『美術とデザインの間』(東野芳明)
(*2)「美術手帖」2019年6月号「特集:80年代★日本のアート」
第2特集「平成の日本美術史 30年総覧−多様化するメディア環境:伊村靖子」(美術出版社)
(*3) ヴィレム・フルッサー、瀧本雅志訳『デザインの⼩さな哲学』(⿅島出版会、2009)原典:1993年