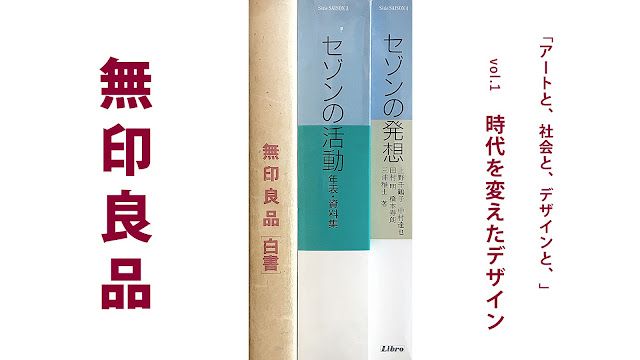時代を変えたデザイン-無印良品
「アートと、社会と、デザインと、 」
vol.1 時代を変えたデザイン-無印良品
開催日:2019年9月7日(土)
時間:18:00‐20:00
講師:伊村靖子 (IAMAS講師)
会費:1,000円
定員:20名 (事前予約制)
1980年12月“わけあって安い”のコンセプトのもと誕生した、無印良品。その背景には二度のオイルショックがあり、高度経済成長が終焉を迎えるとともに、消費への信頼がゆらぎつつありました。無印良品は、パッケージに「わけ」をコピーライティングする大胆な発想で、包装を簡略化し、生産の工程をさらすだけでなく、演出として展開。消費者自身の判断に委ねることにより、消費の過程に個性を復活させ、共感を呼びます。百貨店に店舗を構えながらアンチブランドを掲げる態度には、批評精神が読み取れます。
無印良品が時代を変えた理由について、「生活者のためのデザイン」、「反体制としてのデザイン」という切り口から考えます。
そこから、80年代西武・セゾングループのデザイン・文化戦略を読み解きます。( 伊村靖子・IAMAS講師)
伊村靖子(いむらやすこ/ 情報科学芸術大学院大学(IAMAS)講師)
国立新美術館アソシエイトフェローを経て、2016年より現職。近年は、美術とデザインの関係史に関心を持つ。共編に『虚像の時代
東野芳明美術批評選』(河出書房新社、2013年)。論文に「「色彩と空間」展から大阪万博まで──六〇年代美術とデザインの接地面」(『美術フォーラム21』第30号、2014年)など。関わった展覧会に「美術と印刷物──1960-70年代を中心に」展(東京国立近代美術館、2014年)、岐阜おおがきビエンナーレ2017「新しい時代 メディア・アート研究事始め」(IAMAS、2017年)など。
❖レクチャーシリーズ「アートと、社会と、デザインと、 」について
情報科学芸術大学院大学、通称IAMAS(イアマス)講師の伊村靖子さんによるレクチャーシリーズ「アートと、社会と、デザインと、 」がはじまります。第一弾は「無印良品」と「セゾン文化」を取り上げます。「無印」であることをうたいながら、いまや世界中に広まり、ひとつのブランドとしてのポジションを確立した「無印良品」。もとは80年代に西友のプライベートブランドとしてはじまったこと、忘れている人も多いのではないでしょうか。「無印良品」が当時の消費社会に与えた影響、またそれを仕掛けた、西武・セゾングループの文化戦略とは、どのようなものだったのかをひも解きながら、デザインと社会の関係性について考えます。「セゾン美術館」、「WAVE」、「アール・ヴィヴァン」、「パルコ」・・・セゾン隆盛時代の渦中にいた人も、まだいなかった人も、是非ご参加ください。
IAMAS 伊村靖子さんによる「時代を変えたデザイン-無印良品」にご参加くださいました皆さま、ありがとうございました。
当日は、無印良品が生まれた1980年代に青春を過ごした方々から、三輪車が無印だったという学生の方まで、たくさんお集まりいただきました。またデザイン、建築関係に携わっている方が多く見られ、「無印良品」への関心の高さが伺えました。
お話は意外にも、美術評論家
東野芳明(1930-2005)の言葉から、はじまりました。
実は伊村さん、学生時分より東野芳明を研究していて、詩人の松井茂さんと共に『虚像の時代
東野芳明美術批評選』(河出書房新社、2013年)も出版されています。
『それよりも、問題は観衆の側である。ぼくらは、芸術の問題を考えるとき、芸術家の側ばかりに焦点をあて、その方法論や秘密や意味をひき出すことだけで終わってしまう嫌いがある。芸術が変転し、変質し、さまざまな傾向を生んでゆくのを論じながら、観衆というものは、あたかも、少しも変わらないひとかたまりのデクノボーの大きなマッスとして、論外におかれるのがふつうのようだ。しかし、芸術家の変質が起こっているとすれば、当然、観衆という、茫漠としてはっきりとしないひとつの概念にも変質が起こっているはずであり、その変質を度外視して、現代美術を論ずるのは片手落ちのそしりを免れまい。』(東野芳明「現代観衆論 今日の芸術がめざすもの」/『展望』1967年6月号98頁)
同じく東野が後に語った『文化の主体は、作り手ではなくて、受け手なのだ』(*1)という言葉とともに、この1960年に東野が予言していた観衆論は、いま読んでもはっとするものがあり、今日の美術の状況と照らし合わせて考えてみるのも、また興味深いところです。
しかし伊村さんは、この「(美術は)作ることと見ることとが重なったところで語られるべき」という東野の考え方が、「西武・セゾングループが仕掛けたメディア戦略を通じて、80年代に現実化されていったと解釈できるのではないか」と指摘。これはちょっと思いがけないところからの投げかけです。
東野芳明と西武・セゾン文化。
そんな一見するとつながらなそうな関係を結びつける言葉として、伊村さんがあげられたのは、西武・セゾングループ代表
堤清二の、『消費の過程に、個性を復活させる』でした。そして、当時の社会状況を踏まえながら、「無印良品」をはじめとする一連の文化戦略をたどってみると、そこに「生活者のためのデザイン」、「反体制としてのデザイン」という二つの観点が導き出されるのではないか、と示されました。
〇「生活者」のためのデザイン・・・生産者/消費者の区分を捉え直す
〇「反体制」としてのデザイン・・・資本主義を脱コード化する
世の中が、それまでの『物質的な豊かさを目標に消費者が共同歩調をとった大衆の時代』(*2)に別れを告げ、『自分らしさを求め、感性を消費や行動の判断基準とする』(*2) 消費者、つまり新たな"受け手"が現われはじめたことを受け、西武・セゾングループは、その意識動向に注目しながら、企業として様々な提案を打ち出すことで、新たな消費のかたちを生み出そうとしました。『生産者/消費者の区分を捉え直し』、消費者の意識に働きかけることで、その在り方をも問おうとする、西武・セゾングループの戦略は、先の東野の言葉と通じます。
消費する行為自体に価値や意味を見出したい、という消費者のあらたな欲求は、まさに量から質へと、世の中のものの在り方を変えていきました。また、折りしもバブル時代、巷では空前のブランドブームに沸く一方、ブランドだけを頼りにものを選択する志向より、自分にあったもの、自分らしさを表現することで、生活に精神的充足を求めたいという生活意識を持つ人たちが増えはじめます。そんな中、他社のノーブランド商品が低価格の追及を中心としたのに対し、従来の「消費者」ではなく、新たな「生活者」への提案として、『素材の選択』『工程の点検』『包装の簡略化』と言った、品質の維持に重点を置いた「無印良品」が、1980年、小池一子の『わけあって、安い』のキャッチコピーと、田中一光のアートディレクションにより、誕生したのです。
"ブランド"に対して"無印"であること。
いまや"MUJI"として世界中に展開する"ブランド"でありながら、当時から"no-brand"を標榜する"無印良品"に対して、伊丹十三のこんな言葉が紹介されました。
『木づくりの家に、白木の家具で、若干アンティックを配して、木綿を着て、「無印良品」の缶詰を食べる、これが自分のライフスタイルだと思って気がついてみると、そういうライフスタイルもまた企業によってパッケージされてしまっているというやりきれなさがあるんじゃないですかね』(*3)
また伊丹は、無印良品を『記号の氾濫を通り抜けたところに見出された、ひとまわり上の素朴な記号』として評しました。これについて伊村さんは、「ブランドを否定しながらも、その実、自らブランド化している、という表面的な揶揄を越えた、文明批評(資本主義を脱コード化する)としての可能性を(伊丹は)評価している」のだと、説明されました。
具体的には、
〇資本主義の脱コード化、それは、ブランドの有名性や体裁に惑わされるのではなく、自身でものを見極められる人という付加価値を与える
〇所有することによって、知的・文化的なニュアンスを与える
〇高級化・高品質化と対極にある価値との両端の振幅のなかに、価値を与える
といったことを例に挙げ、この「無印であることの二重構造」は、「生活者像をめぐる"両義性"」を含んでいるのだ、としながら、伊村さんは「大量生産と消費の対象でしかなかった商品イメージを、アートの領域に持ち込むことにより、観客自身の日常をクローズアップしてみせた、ポップアートの手法にも通じるのではないか」と指摘しました。無印良品とポップアート(!)、考えたこともありませんでしたが、確かに、環境にやさしく、シンプルでナチュラルなイメージ覆われた、無印良品の「反体制」としてのデザインは、大量消費と従来の伝統的な美術の在り方へのアンチテーゼという側面を持ったポップアートに、通じるものがあります。
物質的充足と精神的充足、ブランドとアンチ・ブランド、サブカルチャーとハイカルチャー。「反体制」でありながら、それを真向から否定するのではなく、相対するものを両義的に上手く取り入れていく手法こそ、セゾンの文化戦略のひとつなのです。
堤清二は、1975年に西武美術館で開催した「日本現代美術の展望」展のカタログに、「時代精神の根據地として」と題して以下のような文書を寄せています。
『___美術館が街のただ中に建っているということは、空間的な意味ばかりでなく、人々の生活のなかに存在することに通じているべきだと思います。ここで例外的に私達が一つの主張を述べるのは、美術を重要なジャンルとする芸術文化の在り方が、生活と、ことに大衆の生活との奇妙な断絶の関係を持っているという認識に立っているからです。___』
『美術が大衆の生活と奇妙な断絶の関係を持っているという認識に立っている』。
西武美術館(後のセゾン美術館)、西武劇場(現在のパルコ劇場)や銀座セゾン劇場(現在のルテアトル銀座by PARCO)、シネ・セゾン渋谷、シネ・ヴィヴァン六本木、八ヶ岳音楽堂、美術書や洋書を扱ったアール・ヴィヴァン、リブロ、音楽ソフトのWAVEなど、現代の文化を発信する"場所"を次々と設けていった背景には、私たちの生活と文化とは本来地続きであるという考えがあり、それらの”場所”が人々の”精神の根拠地”となることを目指すことが、堤清二の理念だったのです。そこへ足を運ぶこと自体が知的で文化的な体験である、ということをうながしながら、文化の受け手を生み出そうとする。そこで冒頭の東野芳明の「文化の主体は、作り手ではなくて、受け手なのだ」という言葉がじわりと、響いてきます。
消費も文化も、人があってこその行為であると。
「当事者でなければ語ってはいけないのか。」
伊村さんご自身も1979年生まれであり、バブル時代はまだ幼少期で、気がついた時には無印良品があったという世代です。ひと通りお話された後、きっと当時その渦中にいて、西武・セゾン文化を担っていた人たち、またそれをリアルに見聞きした人たちの経験、知見には、遠く及ばないことは承知であるとしながら、当時の状況を経験していないからこそ、冷静に分析し、解釈できることがあるのではないかと、話されたのが、印象的でした。
また質疑応答では、お客さまからも、アメリカの「Whole Earth Catalogue(ホール・アース・カタログ/1968年-1974年)」や、日本での実験的ラジオ放送「St.GIGA(セント・ギガ/1991年-2003年)」など、80年代前後に見られた、メディアやジャンルの枠組みを越えた先進的な試みを、若い人たちが今の感性で紐解くことで、新しい発見や解釈が生まれるのではないか、という意見もありました。世代や地域によって受け取り方が違うなかに、それぞれの西武・セゾン文化がある。そのこと自体が、受け手の多様な受容性によって、豊かな文化が育まれることを、示しているように思いました。
デザインの仕事をしているという若い方からは「消費に個性を、というのは、いまだに現場で言われていることで、驚いた」、というお声や、「当時を知らないので、難しく思える話もあったけれど、それがかえって刺激になって来てよかった」、また当時を見聞きしていた方も、「デザインと商業の話だと思っていたのに、そのベースに美術的な思考があったことが分かって、面白かった」という感想をいただきました。
今回のこのまとめも、西武美術館が開館した1975年生まれの筆者の興味と耳を通して、まとめられています。そのため、伊村さんのレクチャーを正確に記録したものではないこと、ご承知おきいただけましたら幸いです。
最後になりましたが、長い時間をかけて丹念に調べ上げられたことを、こうしてお聞かせくださった、伊村靖子さんにお礼申し上げます。
ありがとうございました。
(*1)「日記から-堂々たる受け手」『曖昧な水 レオナルド・アリス・ビートルズ』(現代企画室、1980年)*初出は1980年3月27日「朝日新聞」夕刊
(*2)藤岡和賀夫「さよなら、大衆」(PHP研究所、1984年)
(*3)『感性時代』(小池一子との対談より/リブロポート/1984年6月1日143頁)